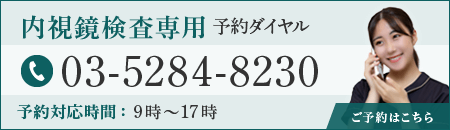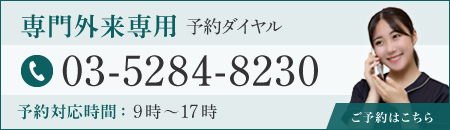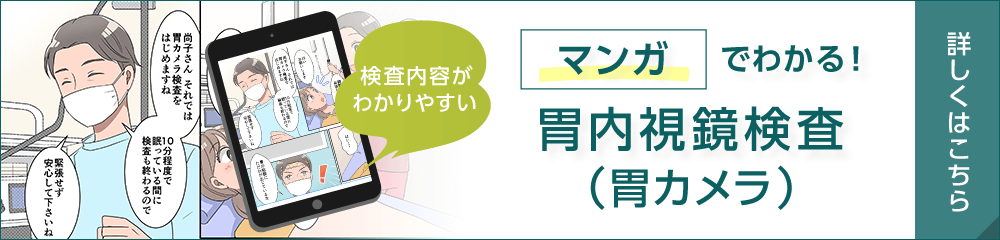「ピロリ菌ってどういうものなの?」
「聞いたことはあるけど、何が問題なの?」
「胃カメラを受けないといけないのかなぁ?」
こういった疑問を持つ方は多いかと思います。
ピロリ菌は、細菌の一種で人体にさまざまな影響を及ぼす病原菌です。胃や十二指腸などの消化管に長期間住みつくことで、慢性的な炎症(ピロリ感染胃炎)を引き起こします。炎症が悪化すると、胃や十二指腸に潰瘍ができることもあります。潰瘍になると胃の痛みや、黒い便が出るなどの症状が現れる場合があります。
さらに、ピロリ菌の感染によって胃がんのリスクが高くなるとも言われています。そのため、感染が確認された場合には、除菌治療が必要です。
この記事では、ピロリ菌の症状・原因・治療法、そしてなぜ胃カメラが必要なのかについて、詳しく解説していきます。
1章 ピロリ菌とは?
ピロリ菌の正式名称は、ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)です。ピロリ菌感染症とは、この細菌が胃に感染することで起こる病気を指します。日本では、全人口の約35%が感染しているとされています。
ピロリ菌感染は、胃や十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因の一つとされています。これらの症状が出た場合には、医療機関でピロリ菌検査を受けることが重要です。症状がなくても、将来的な胃がんの予防を目的に、感染の有無を調べることは大切です。
1-1 ピロリ菌感染症の症状
慢性胃炎の段階では症状が出ないこともありますが、症状が現れるとすれば以下のようなものが代表的です。
ピロリ菌による症状の多くは、胃炎や胃・十二指腸潰瘍に関連しています。通常、胃や十二指腸は粘膜によって守られていますが、炎症によりダメージが蓄積すると、潰瘍が形成されやすくなります。
胃や十二指腸潰瘍ができると、以下のような症状が出ることがあります。
- 胃(腹部)の痛み、またはズキズキするような痛み
- 空腹時に悪化する胃の痛み
- 吐き気
- 食欲の減退
- げっぷが続く
- お腹の膨満感
- 体重減少
では、どんな時に医療機関で診察を受けるべきなのでしょうか?
以下のような重度の症状がある場合は、すぐに医師の診察を受ける必要があります。
- 睡眠中に目が覚めるほどの激しい腹部の痛み
- 黒色便(タール便)
- 血が混じった、または黒色・コーヒーかすのような嘔吐物
潰瘍による出血があると、黒色便や吐血が起きることがあります。出血が続くと貧血など健康への重大な影響が出る可能性もあります。重症化すると、消化管が狭くなり、食べ物の通過が妨げられることもあります。
こうした症状がある場合には、放置せず速やかに医師の診察を受けましょう。
1-2 ピロリ菌感染の主な原因は?
ピロリ菌は、感染者の唾液や体液との接触、あるいは汚染された食べ物や水を通して感染することがあります。特に、衛生環境が整っていない発展途上国などでは感染率が高いとされています。
小児期の生活環境が感染に影響する
ピロリ菌は主に小児期に感染すると考えられています。以下のような生活状況がリスクとされています。
- 集団接触:兄弟姉妹が多い家庭や同居人数の多い家では感染リスクが高まります。
- 下水環境の未整備:衛生環境が整備されていないと、感染リスクが高くなります。
- 発展途上国での生活:水や食べ物の衛生状態が悪い地域では感染率が高くなります。
- 家族内感染:ピロリ菌に感染している家族と同居していると、感染の可能性が高くなります。
2章 ピロリ菌は怖い?合併症について
ピロリ菌感染に関連する主な合併症には、以下のような消化器系の病気があります。
- 胃・十二指腸潰瘍
- ピロリ感染胃炎
- 胃がん
- 胃MALTリンパ腫
- 胃過形成性ポリープ
- 貧血
それぞれの病気について、詳しく見ていきましょう。
2-1 胃潰瘍
ピロリ菌は、胃や十二指腸の粘膜を傷つけることで、潰瘍を引き起こす可能性があります。
統計的には、ピロリ菌に感染した人の約10%が潰瘍を発症します。逆に、十二指腸潰瘍の約90%、胃潰瘍の最大80%はピロリ菌が原因とされています。
感染によって粘膜が傷つくと、胃酸が内壁を刺激し、潰瘍が形成されます。
潰瘍の症状としては、以下が挙げられます。
- 空腹時に悪化する腹痛や不快感
- 灼熱感を伴う腹痛
- 膨満感
- げっぷが続く
- 胸焼け
- 吐き気
- 原因不明の体重減少
- 吐血
- 黒色便
2-2 ピロリ感染胃炎
ピロリ菌感染により、胃粘膜に慢性の炎症(ピロリ感染胃炎)が生じます。長期化すると、萎縮性胃炎へと進行する可能性があります。
症状が出ないこともありますが、以下のような症状がみられることもあります。
- 上腹部の灼熱感
- 消化不良
- 吐き気
- 嘔吐
この胃炎が進行すると、潰瘍や出血、胃のポリープ(胃過形成性ポリープ)、さらに胃がんへとつながることもあります。
2-3 胃がん
ピロリ菌は胃がんの大きなリスク因子とされています。未感染者でも胃がんは発症しますが、発症メカニズムや部位が異なる傾向があります。
症状がない状態でも感染の有無を調べておくことで、将来的な胃がんの予防に役立つとされます。感染者であれば、除菌治療の対象となる可能性が高いです。
2-4 胃MALTリンパ腫
ピロリ菌感染が原因で、胃にリンパ腫ができることがあります。特に胃MALTリンパ腫(粘膜関連リンパ組織リンパ腫)は、悪性度が比較的低く、良性の経過をたどることが多いです。
このタイプのリンパ腫は、ピロリ菌を除菌することで改善することが知られています。
一方で「びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)」といった悪性度の高いタイプの場合には、慎重な治療が必要です。
2-5 胃過形成性ポリープ
胃過形成性ポリープは、胃にできる赤みの強いポリープで、大きくなるとがん化したり出血を起こして貧血の原因になることもあります。
ピロリ菌を除菌することでポリープが小さくなったり、自然に消えることもあります。
2-6 貧血
鉄分が不足することで起こる「鉄欠乏性貧血」は、ピロリ菌感染が原因となっている場合があります。
ピロリ菌に感染していると、鉄分の吸収を助けるアスコルビン酸(ビタミンC)の濃度が低下することがあり、それによって鉄が十分に吸収されなくなります。
鉄剤のみでは改善が見られなかったケースでも、除菌治療を併用することで貧血が改善することがあると報告されています。
こうした症状や合併症が心配な方は、当クリニックの消化器専門外来までご相談ください。
3章 ピロリ菌はどうやって治療するの?
それでは、ピロリ菌は実際にどのように治療されるのでしょうか?
3-1 ピロリ菌の治療
ピロリ菌は、薬を服用することで治療することができます。日本では2013年より、除菌治療が保険適用となり、多くの患者さんが治療を受けるようになりました。
治療は、2種類の抗生物質と胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬またはP-CAB)を組み合わせて行います。
この治療によって、慢性胃炎の改善や潰瘍の治癒が期待できるほか、潰瘍の再発や出血の予防にもつながります。
また、ピロリ菌の除菌によって、将来的な胃がんの予防にも効果があるとされています。
3-2 ピロリ菌治療に使われる薬
ピロリ菌感染症は薬物療法が基本です。ピロリ菌は細菌のため、抗生物質による治療が行われます。また、同時に胃酸の分泌を抑える薬も併用します。
① 抗生物質
通常、2種類以上の抗生物質を併用して服用します。これは、耐性菌を防ぐためでもあります。
抗生物質は適切に服用しないと、細菌が薬に耐性を持ち、治療が困難になることがあるため注意が必要です。
また、薬による副作用が出ることもあるため、医師の指示のもとで服用してください。
② 胃酸生成を抑える薬
- プロトンポンプ阻害薬(PPI)
- ヒスタミン受容体遮断薬(H2ブロッカー)
- カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)
PPIは、胃で酸を生成するポンプの働きを抑え、胃内の酸の量を減らす薬です。
主なPPIの種類には、次のような薬があります。
- エソメプラゾール
- ランソプラゾール
- オメプラゾール
- パントプラゾール
- ラベプラゾール
ヒスタミン(H2)受容体遮断薬は、酸の分泌を促すヒスタミンという物質の作用をブロックします。具体的には、シメチジン、ファモチジン、ニザチジンなどがあります。
ただし、H2遮断薬は副作用や効果の面から、PPIやP-CABが使えない場合に代替として使用されます。
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)は、胃酸の生成を抑える新しいタイプの薬であり、ボノプラザンという成分が代表例です。
P-CABは、除菌成功率が高いことから、最近ではピロリ菌治療でよく使用されます。
なお、薬物療法で除菌に失敗した場合には、抗生物質の組み合わせを変更した二次除菌が必要となることがあります。
3-3 治療には、一次除菌と二次除菌がある
ピロリ菌の除菌治療は、保険診療で2回まで認められており、1回目を一次除菌、2回目を二次除菌と呼びます。
一次除菌では、ボノプラザンを使用した場合、除菌成功率は約90%に達するとされています。
除菌治療は、抗生物質2種と胃酸抑制薬1種の「3剤併用療法」で行われます。
一次除菌の例
以下は、一次除菌の代表的な治療内容です。
- アモキシシリン 250mgカプセル:1回3カプセル・1日2回
- クラリスロマイシン 200mg錠:1回1錠・1日2回
- ボノプラザン 20mg錠:1回1錠・1日2回
上記の組み合わせを7日間服用します。
二次除菌の例
一次除菌に失敗した場合には、以下のような二次除菌が行われます。
- アモキシシリン 250mgカプセル:1回3カプセル・1日2回
- メトロニダゾール 250mg錠:1回1錠・1日2回
- ボノプラザン 20mg錠:1回1錠・1日2回
こちらも同様に7日間投与されます。
除菌治療の後には、きちんと除菌できたかどうかの効果判定(除菌判定検査)が必要です。
この判定は、除菌治療終了後4週間以上あけてから行います。主に次のような方法で行われます。
- 尿素呼気試験(UBT)
- 便中ピロリ抗原検査
注意点として、検査の直前2週間以内に抗菌薬や胃薬(PPIやP-CAB)を服用していると、検査結果が正確に出ないことがあります。そのため、検査前にはこれらの薬を中止する必要があります。
なお、血清ピロリ抗体検査や迅速ウレアーゼ試験は、除菌効果判定には適していません。
除菌や検査についてのより詳しい説明を聞きたい方は、以下のような点を医師にご相談ください。
- ピロリ菌感染による合併症について
- 検査や治療の方法・必要性
- 検査に際しての注意点
- 治療の成功判定の方法
4章 ピロリ菌の診断方法や検査は?
ピロリ菌に感染しているかどうかを判断するには、いくつかの検査が用いられます。
また、除菌治療を行ったあとは、きちんと除菌できているかの確認も重要です。
以下に、代表的な検査方法をまとめます。
- 抗ヘリコバクター・ピロリ抗体測定(血液)
- 便中ピロリ抗原測定
- 便PCR検査
- 尿素呼気試験(UBT)
- 内視鏡検査(迅速ウレアーゼ試験・鏡検法・培養法)
それぞれの検査方法について、以下で詳しく解説していきます。
4-1 抗ヘリコバクター・ピロリ抗体測定
血液検査により、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。陽性であれば、感染している可能性が高いと判断されます。
この検査で陽性と診断された場合は、胃カメラを行い、実際に胃内に炎症があるかなどを確認します。
4-2 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原測定
便の中に含まれるピロリ菌の抗原(タンパク質)を調べる検査です。
検出率も高く、一般的な診断法としてよく使われています。
4-3 便PCRテスト
PCR検査では、便の中に含まれるピロリ菌の遺伝子を検出することができます。
また、抗生物質に対する耐性を示す遺伝子変異も検出できるため、除菌治療の薬剤選定にも役立ちます。
ただし、便中抗原検査よりもコストが高く、すべての医療機関で実施できるわけではありません。
4-4 尿素呼気試験(UBT)
ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を出し、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解します。
その仕組みを利用して、呼気に含まれる二酸化炭素の濃度を測定することで、ピロリ菌の有無を調べるのが尿素呼気試験です。
非常に精度が高く、除菌後の判定にも用いられます。
4-5 胃内視鏡検査(胃カメラ)
胃カメラを行うことで、萎縮性胃炎や潰瘍の有無など、ピロリ菌感染の兆候を直接確認できます。
必要に応じて胃粘膜の組織を採取し、以下のような方法でピロリ菌の有無を検査します。
- 迅速ウレアーゼ試験
- 鏡検法
- 培養法
5章 ピロリ菌の診断・治療には胃カメラが必須
他の検査でピロリ菌の感染が判明しても、保険診療による除菌治療を行うには、胃カメラで萎縮性胃炎が確認されていることが条件になります。
また、胃カメラでは以下のような病気の有無も同時に調べることができるため、非常に重要です。
- 胃がん
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
- 胃MALTリンパ腫
除菌後も定期的な検査を!
ピロリ菌を除菌したとしても、胃がんのリスクが完全にゼロになるわけではありません。
そのため、除菌後も定期的に胃カメラによる内視鏡検査を受けることが大切です。
除菌後に発生する「除菌後胃がん」については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
まとめ
今回は、ピロリ菌に関する基礎知識から治療方法まで、幅広く解説しました。
ピロリ菌に感染していても、すぐに症状が出るとは限りませんが、放置しておくと慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクが高まります。
本記事でのポイントは以下の通りです。
- ピロリ菌に感染すると、慢性的な胃炎を引き起こす
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因になる
- 感染していると胃がんのリスクは非感染者の約15倍になる
- ピロリ菌は薬を内服することで治療(除菌)可能
- 除菌治療には、胃カメラで萎縮性胃炎の確認が必要
感染が判明した場合には、年齢や体調を考慮しつつ、除菌療法を検討することをおすすめします。
また、除菌後も油断せず、継続的に内視鏡検査を受けることが、胃がんの予防につながります。
当クリニックでは、ピロリ菌の除菌治療および内視鏡検査を、日本ヘリコバクター学会のガイドラインに基づいて行っています。
不安なことや治療のご相談がある方は、お気軽に消化器専門外来までお越しください。
※この記事は2022年6月16日に公開され、2023年4月5日に一部修正、2025年6月23日に更新されました。
参考文献
- H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2016改訂版
- Warren JR. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983
- Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomachs of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分