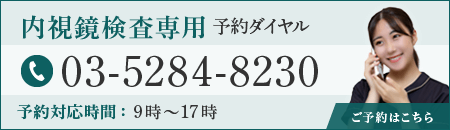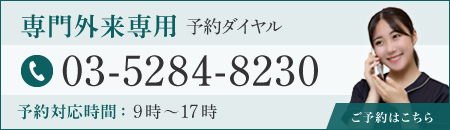潰瘍性大腸炎は年々、患者さまが増え続けている病気です。
20代で発症することも多い疾患であり、重症化すると手術を行わなければいけません。
「潰瘍性大腸炎を発症する原因は?」
「潰瘍性大腸炎を疑う場合はどんな検査をするの?」と気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、潰瘍性大腸炎の発症原因や診断方法、治療法について詳しく解説します。
腹痛や下痢などを繰り返す方は、潰瘍性大腸炎の可能性があります。症状を放置せず、悪化する前に検査を受けることが大切です。
大腸検査を受けたいと考えている方は、消化管検査の経験豊富な医師がいる東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックにお越しください。当院は千住駅徒歩2分の場所にあり、土日も検査を受けることができます。女性医師の在籍や女性専用スペースもあり、女性の方でも周りの目を気にすることなく検査を受けられます。
早期に潰瘍性大腸炎の治療を始めるために、ぜひ当施設の大腸の検査を受けてみませんか。
目次
潰瘍性大腸炎とは?
潰瘍性大腸炎は、大腸の内壁に炎症や潰瘍ができる慢性疾患です。治療を続けていても、長期での管理が必要であり、症状を繰り返します。長く付き合っていかなくてはならない病気です。
症状が悪化しているときには、トイレに何度も行ったり、お腹が痛くなったりとつらい思いをする人も少なくありません。さらに、バランスのよい食生活を続けていかなければならず、好きな時に好きなものを食べられないこともあるため、ストレスが溜まる人もいます。
潰瘍性大腸炎は完治が難しい病気ですが、適切な治療と生活習慣の改善により、症状を管理することは可能です。症状が落ち着いていれば、日常生活に支障をきたすことはありません。
症状をコントロールするためには、早期に発見し、定期的に医師の診察を受け、自己管理をしていくことが重要となります。
潰瘍性大腸炎の患者数
潰瘍性大腸炎は、世界中で増加傾向にある慢性炎症性腸疾患です。日本においても、患者数は年々増加しています。最新の統計によれば、日本では約16万人以上が潰瘍性大腸炎を患っているとされています。人口10万人あたりおよそ100人の割合です。
とくに男性では20〜24歳、女性では25〜29歳に多く見られますが、実際にはあらゆる年齢層で発症する可能性があります。潰瘍性大腸炎は長期の治療が必要な病気ですが、死亡例は少なく、命を直接脅かす病気ではありません。
潰瘍性大腸炎と診断されると大きな不安を感じる方も多いでしょう。しかし、正しい治療を継続すれば症状はコントロールでき、ほとんど症状がなく生活できる方も少なくありません。専門医にしっかり診てもらい、安心して治療を続けていくことが大切です。
潰瘍性大腸炎の原因は明らかになっていない
「なぜ潰瘍性大腸炎を発症するのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
潰瘍性大腸炎の原因は完全には分かっていませんが、免疫系の異常や腸内環境、食生活習慣などが関わっていると考えられています。以下で代表的な要因を見ていきましょう。
自己免疫異常
潰瘍性大腸炎の原因のひとつに自己免疫異常があります。自己免疫異常とは、免疫系が自分の体の組織を誤って攻撃する状態です。免疫の異常が起こる背景には、以下のようなものが考えられます。
- 感染症
- 薬の副作用
- 遺伝的な体質
- 生活習慣の乱れ(不規則な食生活、肥満、過度なストレスなど)
潰瘍性大腸炎の場合、免疫系が大腸の粘膜を異物と誤認し攻撃するため、炎症や潰瘍が生じます。その結果、腹痛や血便などの症状が現れます。
腸内細菌の乱れ
腸内細菌のバランス異常も原因のひとつとされています。腸内フローラは消化や免疫を支える重要な役割を担いますが、バランスが崩れると免疫反応が過剰に働き、大腸の粘膜に炎症を起こしてしまいます。
食生活習慣やストレス
脂肪分の多い食事や加工食品の摂取は、腸内環境を悪化させ免疫に悪影響を与えます。さらに、生活リズムの乱れや精神的ストレスも発症や悪化に関わっていると考えられます。
潰瘍性大腸炎に伴う合併症
潰瘍性大腸炎は大腸のみに炎症が起こる病気ですが、長期的には以下のような合併症がみられることもあります。
- 関節炎:手足や腰などに痛みが出ることがあります。
- 皮膚症状:赤みやしこりなどの皮膚炎を伴う場合があります。
- 眼の炎症:ぶどう膜炎や虹彩炎など目のトラブルを起こすケースもあります。
- 大腸がんのリスク:長期間炎症が続くと、将来的に大腸がんのリスクが高まることが知られています。
合併症を早期に防ぐためには、定期的な内視鏡検査や血液検査で状態をチェックすることが欠かせません。
潰瘍性大腸炎の症状
潰瘍性大腸炎は、大腸の内壁に炎症や潰瘍が生じる慢性疾患で、さまざまな症状を引き起こします。主な症状には以下のようなものがあります。
- 腹痛
- 下痢(ときに血が混じる)
- 血便
- 体重減少
- 疲労感
- 発熱 など
大腸の炎症により下腹部に強い痛みを感じ、下痢や血便の症状が繰り返し現れます。さらに、消化吸収の不良や食欲不振により体重が減少することもあります。
慢性的な炎症は全身のエネルギー消費を増やすため、強い疲労感を伴うことも特徴です。重症例では発熱や貧血を起こすこともあり、日常生活に大きな支障をきたします。
特に若い方で血便が続く場合には、痔による出血ではなく、潰瘍性大腸炎の可能性もあります。その理由については、「なぜ若い人の血便は潰瘍性大腸炎を疑うべきなのか?」でも詳しく解説しています。
潰瘍性大腸炎の検査・診断方法
潰瘍性大腸炎を診断するためには、いくつかの検査が行われます。症状や病歴を踏まえ、医師が総合的に判断します。
- 血液検査(炎症の有無や貧血の確認)
- 便培養(感染性の下痢との区別)
- 腹部CT・MRI(炎症範囲や合併症の有無を確認)
- レントゲン検査
- 大腸内視鏡(潰瘍や炎症の直接観察、組織採取)
特に大腸内視鏡は、炎症の広がりや重症度を評価するうえで欠かせない検査です。組織を採取し病理検査を行うことで、がんや他の腸疾患との区別も可能になります。
潰瘍性大腸炎の検査方法や治療の流れについては、「潰瘍性大腸炎の検査は何がある?内容や治療方法まで詳しく解説!」でさらに詳しく紹介しています。検査を検討中の方はぜひご覧ください。
大腸カメラ検査の前には、腸の中をきれいにするための下剤処置が必要です。当院では、プライバシーに配慮した半個室や個室をご用意しており、安心して前処置を受けていただけます。
日常生活でできる工夫
潰瘍性大腸炎は長期的に付き合う必要のある病気です。そのため、治療と並行して日常生活でできる工夫も大切です。
- 食事の工夫:脂っこい食事や刺激の強い香辛料を控え、消化の良い食品を選びましょう。
- 規則正しい生活:睡眠不足や過労は症状悪化の原因となるため、生活リズムを整えることが大切です。
- ストレス対策:ヨガや軽い運動、趣味の時間などで心身をリラックスさせることが有効です。
- 水分補給:下痢が続くと脱水になりやすいため、こまめな水分補給を心がけましょう。
- 定期検診:自覚症状が落ち着いていても、定期的に内視鏡検査を受けて炎症やがん化の有無を確認することが重要です。
これらの工夫を取り入れることで、症状の悪化を防ぎ、再燃を抑える効果が期待できます。医師の指導のもとで、自分に合った生活スタイルを整えていきましょう。
潰瘍性大腸炎の治療方法
潰瘍性大腸炎の治療方法は、主に薬物療法と手術です。症状や重症度に応じて最適な方法が選択されます。
薬物療法で完治するわけではありませんが、大腸の炎症を抑え、症状が悪化しないようにすることが目的です。抗炎症薬や免疫抑制薬、生物学的製剤などが処方されます。
そして、以下のような場合には外科手術が必要となることがあります。
- 症状が重く日常生活に大きな支障がある場合
- 薬物療法が効果を示さない場合
- 出血が多い場合
- 腸に穴(穿孔)が空いた場合
- 大腸がんが発見された場合、もしくはがん化が強く疑われる場合
外科手術では大腸の一部または全体を切除します。切除範囲によっては、人工肛門を造設するケースもあります。
治療後の経過観察と再発予防
潰瘍性大腸炎は治療によって症状をコントロールできても、再発(再燃)する可能性があります。そのため「治療が終わったから安心」ではなく、経過観察が欠かせません。
- 定期的な内視鏡検査:炎症の有無や大腸がんの早期発見に役立ちます。
- 血液検査や便検査:炎症マーカーや出血の有無をチェックします。
- 薬の継続:症状が落ち着いていても、医師の指示に従い維持療法を続けることが重要です。
- 生活習慣の改善:規則正しい生活や食事の工夫は再燃防止につながります。
潰瘍性大腸炎は「寛解」と「再燃」を繰り返す病気です。再燃を防ぐためには、医師と相談しながら計画的に経過観察を続けていくことが大切です。
潰瘍性大腸炎と向き合う心のケア
潰瘍性大腸炎は身体的な症状だけでなく、精神的なストレスも伴いやすい病気です。長期的な治療や生活制限により、不安や孤独感を抱く方も少なくありません。
- 医師や医療スタッフとの相談:症状や悩みを遠慮せず伝えることで安心につながります。
- 家族や周囲の理解:病気について共有することで、サポートを得やすくなります。
- 患者会やサポートグループ:同じ病気を持つ仲間との交流は、大きな励みになります。
- ストレス対策:趣味、運動、リラクゼーション法を取り入れることが心身の安定に有効です。
「病気と上手に付き合うこと」も治療の一部です。心のケアを意識することで、日常生活をより前向きに過ごせるようになります。
潰瘍性大腸炎が疑われる場合は当院へ
潰瘍性大腸炎は、大腸内の炎症と潰瘍を引き起こす慢性の炎症性腸疾患です。症状には、腹痛や下痢、血便、体重減少、発熱などがあります。
自己免疫異常や腸内細菌、食生活習慣などが原因と考えられています。
潰瘍性大腸炎を診断する検査は、血液検査や大腸内視鏡検査、腹部CTなどです。治療法としては薬物療法が中心で、抗炎症薬や免疫抑制薬などが使用されます。重症の場合は外科手術が必要です。
潰瘍性大腸炎の重症化を防ぐには、早期に適切な治療を始めることが大切です。
下痢や腹痛、血便などで悩んでいる方は、東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックへご相談ください。経験豊富な医師が大腸内視鏡検査をはじめとする消化管検査を行います。大腸前処置は完全個室や半個室を完備しているため、周囲の目を気にする必要はありません。また、女性専用スペースや女性医師も在籍しているため、女性の方も安心して検査を受けていただけます。
忙しい方やお仕事前に検査を済ませたい方には、朝から受けられる「モーニング大腸カメラ検査」もご用意しています。効率よく健康管理をしたい方におすすめです。
当院での大腸カメラ検査は、WEBまたはLINEから簡単にご予約いただけます。
ご予約後は、検査前に必要な準備や注意点についてスタッフが丁寧にご案内しますので、初めての方も安心して受けられます。
※この記事は2024年8月30日に公開され、2025年8月19日に更新されました。
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分