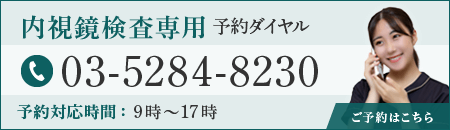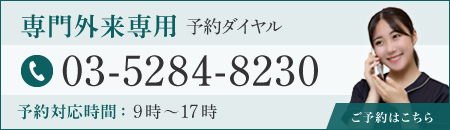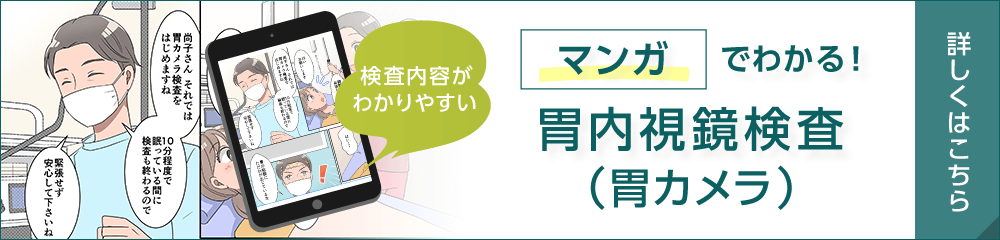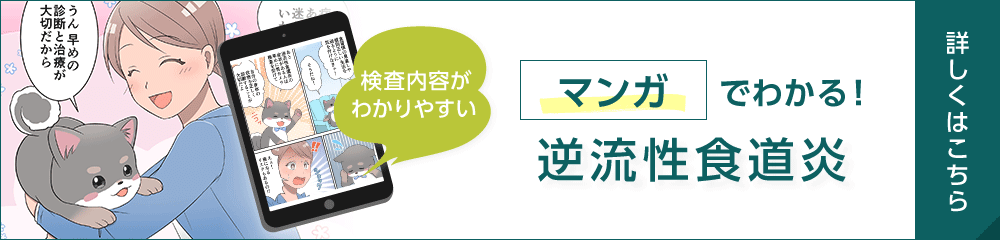「もしかして逆流性食道炎かも…」
「逆流性食道炎かどうか、簡単にチェックする方法が知りたい」
胸や口の中に胃からの内容物が逆流しているのかなと感じた場合には、逆流性食道炎かもしれないと疑う方が多いのではないでしょうか。逆流性食道炎になると、胸や胃がムカムカしたり酸っぱいものが上がってきたりするため、日常生活に支障が出ることがあります。
このような症状が出た場合、逆流性食道炎の可能性があるのかチェックしておきたいと考える方もいるでしょう。そこで今回は、逆流性食道炎かどうかをセルフチェックする方法について紹介します。治療方法や対策についても解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
目次
1章 逆流性食道炎とは
逆流性食道炎とは、胃の内容物が逆流することで食道粘膜が炎症を起こした状態のことです。おもに胃酸が逆流します。胃酸はpH1~2と、非常に酸性度の高い物質です。これは、鉄をも溶かしてしまうほどの力があることで知られています。
胃には胃酸から守るための粘膜が存在するため、これだけ強い酸性条件下にさらされても溶けてしまうことがありません。しかし、食道粘膜には胃酸から守るための働きが備わっていないため、胃酸にさらされるとダメージを受けてしまうのです。
胃酸の逆流を繰り返していると、次第に食道がただれたり潰瘍ができたりします。成人の5~10人に1人が発症していると言われている病気です。
1-1 逆流性食道炎で見られる症状
逆流性食道炎になると、次のような症状が良く見られます。
- 胸焼け
- 胸痛
- 咳
- のどの違和感
胃の内容物が逆流することで食道に炎症が起こるため、胸焼けや胸痛などが見られます。また、逆流した胃液によって喉や気管支が刺激されるため、咳やのどの違和感が出ることもあるでしょう。
1-2 逆流性食道炎の原因
通常は下部食道括約筋がしっかり働くことで、胃と食道の間はほとんど隙間なく閉じた状態になっています。しかし、下部食道括約筋がゆるむと、簡単に胃の内容物が逆流してしまうため、逆流性食道炎を引き起こしてしまうのです。
下部食道括約筋がゆるむ原因としては、加齢が挙げられます。年を重ねると、体全体の筋力が落ちていくのと同じで、下部食道括約筋の働きも落ちてしまうのです。
このほか、横隔膜にある食道裂孔がゆるんだり、胃酸が増加したりすることも原因となります。食事内容や肥満、腹圧なども逆流性食道炎の原因です。脂肪分の多い食事の摂り過ぎは、胃酸を増やしてしまうため、逆流を起こしやすくします。また、たんぱく質の多い食事は消化に時間がかかるため、こちらも胃酸の逆流を起こしやすくする要因です。
肥満になると逆流性食道炎になりやすくなるのは、お腹に脂肪がつくことで自然と腹圧が上がってしまうことが関係しています。腹圧が上がると、胃が締め付けられたような状態になるため内容物が逆流しやすくなるのです。妊娠していたり背中が曲がっていたりする方も腹圧が上昇するため、逆流を起こしやすくなります。
1-3 逆流性食道炎になりやすい方の特徴
次のような方は逆流性食道炎を発症しやすいので注意しましょう。
- 脂質が多い食事を良く摂る方
- 高齢の方
- 背中が曲がっている方
- 肥満の方
- 妊娠している方
- ピロリ菌の除菌治療を受けた方
脂質の多い食事は胃酸の分泌量を増やすため、内容物が逆流しやすい環境を作ってしまいます。高齢になると、逆流性食道炎になりやすいのは、下部食道括約筋の働きが低下するためです。背中が曲がっている方、肥満の方は腹圧が上昇しやすいため内容物が逆流しやすくなります。
妊娠している方がなりやすいのは、子宮が大きくなることで胃が持ち上げられ、圧迫されるためです。出産すると、自然に症状が落ち着いてくることが多いでしょう。ピロリ菌の除菌治療をした方も要注意です。ピロリ菌を除菌すると胃酸の分泌がこれまでよりも活発になり、逆流性食道炎になりやすくなります。
2章 逆流性食道炎をセルフチェックしてみよう
では、逆流性食道炎の可能性があるかどうかをセルフチェックしてみましょう。次の項目で当てはまるものがあるかチェックしてみてください。
- ☐ 胸焼けがする
- ☐ お腹がよく張る
- ☐ 食事の後に胃がもたれやすい
- ☐ ゲップがよく出る
- ☐ 食事の後に吐き気がすることがある
- ☐ のどに違和感がある
- ☐ 風邪を引いていないのに咳が出る
- ☐ 思わず胸を手でこすってしまうことがある
- ☐ 食事の途中で満腹になることがある
- ☐ 酸っぱいものが上がってくることがある
- ☐ 前かがみになると胸焼けがする
- ☐ ものを飲み込むとつかえることがある
これらの12項目のうち、1つでも該当するものがあれば逆流性食道炎の可能性があります。気になることがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。当院でも逆流性食道炎の診察を行っていますので、お気軽にご相談ください。
逆流性食道炎について、よりわかりやすくまとめたページもご用意しています。
▶ 逆流性食道炎の専門ページはこちら
なお、当てはまる項目があるからといって、必ずしも逆流性食道炎と診断されるというわけではありません。逆流性食道炎の疑いがあると分かった場合は、その後に検査を行い確定診断をすることが大事です。
3章 逆流性食道炎の検査方法
逆流性食道炎が疑われる場合は、検査を行って本当に逆流性食道炎なのかどうかを判断します。胃内視鏡検査を含め、次のような方法で検査が行われることが一般的です。
3-1 問診
症状を問診し、逆流性食道炎と診断することがあります。セルフチェックの方法のところでも紹介したように、「胸焼けがしますか?」「食べた後に気持ち悪くなることがありますか?」などいくつか問診を行い、当てはまる項目数を見て診断をしていきます。
逆流性食道炎が疑わしいと診断した場合には、必要に応じて検査を行います。検査は胃内視鏡検査が一般的です。
3-2 胃内視鏡検査(胃カメラ)
逆流性食道炎が疑われるときに一般的に行われているのが胃内視鏡検査です。いわゆる胃カメラのことで、胃の状態を内視鏡で観察することで診断を行います。「胃カメラは苦しい」と思っている方もいるかもしれませんが、当院では苦痛の少ない胃カメラを行っていますのでご安心ください。静脈麻酔を行い、鎮静した状態で検査を行っています。
当院での胃カメラについては、下記のマンガでわかりやすく解説しています。
3-3 食道内pHモニタリング検査
鼻から管を通し、食道内の酸性度を24時間にわたり継続して測定する検査です。胃酸が逆流している場合はpHが4以下となります。pHが4以下になる時間がどれくらいあるのかによって胃酸が逆流しているかを検査するものです。
3-4 食道内圧測定検査
食道が正常に収縮しているかを調べます。食道内の圧力を調べることで、蠕動運動がきちんと働いているかを調べるものです。同時に、下部食道括約筋の働きも測定します。
3-5 レントゲン検査(食道造影検査)
造影剤を飲んでもらい食道の造影剤の流れを見ることで、下部食道括約筋のゆるみ具合を見る検査です。下部食道括約筋がゆるんでいる場合は、胃酸が逆流しやすくなっているため、逆流性食道炎の可能性があります。現在では胃カメラが一般的であるため行われることはほとんどない検査です。
4章 逆流性食道炎を放置するとどうなるの?
逆流性食道炎による炎症が長引くと、バレット食道に進行することがあります。バレット食道とは、食道の粘膜が胃の粘膜上皮に置き換えられたバレット上皮が広範囲に広がったものです。
バレット食道になっても、とくに自覚できる症状はありません。しかし、バレット食道がある方は、そうでない方と比べて30~120倍も食道がん(バレット食道がん)になるリスクが高くなると言われています。そのため、逆流性食道炎を治療せず放置しておくのはとても危険です。
5章 逆流性食道炎の治療は薬物療法が基本
逆流性食道炎は、胃酸を抑える働きのあるPPI(プロトンポンプ阻害薬)やP-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)などを使って治療していくことが基本です。胃酸を抑える薬で効果が不十分な場合は、消化管の機能を改善する薬や胃粘膜を保護する薬なども使われることがあります。
逆流性食道炎の治療については、▶ 逆流性食道炎の治し方とは?症状・初期治療やお薬について専門医が解説 でも詳しくご紹介しています。
6章 逆流性食道炎かなと思ったらやるべきこと
逆流性食道炎の基本は内服治療ですが、このほかに生活習慣の改善を行うことも大切です。症状が出にくいような環境を整えることで、胸焼けや胃酸の逆流などが起こりづらい状態にできます。
6-1 食後すぐに横にならない
食後すぐに横になるのは止めましょう。胃の内容物が逆流しやすくなります。食後は胃酸の分泌が盛んなため、2~3時間は横にならないようにするのがおすすめです。
6-2 前かがみになる動作を避ける
逆流性食道炎の方では下部食道括約筋がゆるんでいるため、前かがみの姿勢になると、胃の内容物が簡単に逆流してしまいます。できるだけ前かがみの姿勢にならないように注意しましょう。
6-3 胃酸の分泌を促す飲食物を避ける
コーヒーやアルコール、炭酸飲料などは胃酸の分泌を促します。このほか、脂っこい食べ物や甘いもの、酸っぱいものも胃酸分泌を促進するため、摂りすぎないようにしましょう。
7章 逆流性食道炎に関するQ&A
最後に、逆流性食道炎について良く聞かれる質問にお答えします。
Q1 市販のガスター10は逆流性食道炎に効きますか?
市販のガスター10でも逆流性食道炎の症状を抑えることができます。ガスター10は、医療用と同じファモチジンを1錠あたり10mg含む薬です。医療用では20mg配合されたものも扱われています。市販薬で効果が不十分な場合には、さらに効果の高いPPIやP-CABといったお薬の内服が必要となることがあります。そのような場合には、医療機関を受診する必要があります。
Q2 逆流性食道炎が疑われる場合、何科にかかれば良いですか?
逆流性食道炎が疑われる場合は、消化器内科または胃腸科を受診してください。内視鏡検査が必要となることがほとんどですので、内視鏡内科でも問題ありません。
Q3 逆流性食道炎で下痢になることはありますか?
逆流性食道炎で下痢になることがあります。逆流性食道炎の場合には、胃において消化不良を起こす可能性もあるため下痢症状を起こすこともあり得ます。下痢の症状がつらいときは、早めに相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、逆流性食道炎のセルフチェック・症状および治療法を中心に解説しました。本記事のポイントとしては下記のようになります。
- 逆流性食道炎では胸焼けや胸痛などが見られる
- 逆流性食道炎の可能性があればセルフチェックを行う
- 逆流性食道炎が疑われるときには胃カメラを行うのが一般的
- 逆流性食道炎を放置するとバレット食道やバレット食道がんになる可能性がある
逆流性食道炎は、胃の内容物が逆流することで食道粘膜が傷ついた状態のことです。胸焼けがしたり酸っぱいものが上がってきたりなどの症状がある方は、逆流性食道炎の可能性があると考えられます。
放っておくと食道がん(バレット食道がん)に進行することもあるので、症状が気になるときは早めに消化器内科や胃腸科を受診しましょう。
逆流性食道炎と似た症状の中には「吐き気」があります。受診すべき目安については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
当クリニックでは、下記より専門外来および胃内視鏡検査の予約は下記より承っています。
※この記事は2023年3月21日に公開され、2025年6月12日に更新されました。
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分